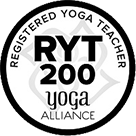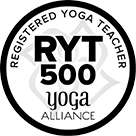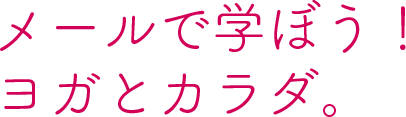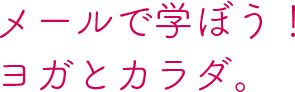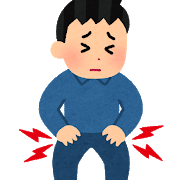扇谷孝太郎のコラム,コラム,ヨガと体のQ&A 2019.11.27
ロルフィングとヨガの親和性
こんにちは、ロルファー™️の扇谷孝太郎です。
わたしが TOKYOYOGA さんで、ヨギの方々向けの講座をするようになって10年が経ちました。
ヨギではないわたしがこんなにも長く講座を続けてこられたのは、調べていくほどにヨガとロルフィングとの親和性に気づかされたからだと思います。
近年、講座でご紹介しているチャクラと動きの関係についての研究は日々のセッションでとても役立っていますが、これもヨガとの出会いがなければわからなかったことです。
わたしにとって、ヨガとロルフィングはきわめて近いところにあります。
ロルフィングがヨガをする上で、なぜ役に立つのか?
筋膜の伸ばし方や解剖学という切り口では、これまでに講座のご案内などでたくさん書いてきたので、ここではわたし自身の体験からお話ししたいと思います。
筋膜、重力、知覚といったロルフィングの視点からヨガのポーズを見ると、その「形」に込められた設計者の意図や配慮に驚かされることがあります。
ヨガはただ筋肉を鍛えたりストレッチするための体操ではなく、人間の可能性をひらき、自由にするための知恵の結晶だと感じるのです。

たとえば、ロルフィングのムーブメントエクササイズを考えていたとき、こんなことがありました。
その日わたしは一人で、重力との調和の中で人間の頭はどのように動くべきなのか?
そのとき、眼は、鼻は、耳は、舌はどうあるべきなのか?
そんなふうに試行錯誤して頭部の動きを探っていました。
そして、ある瞬間、ふと自分の顔がライオンのポーズの顔になっていることに気づきました。
ためしにそのまま背筋を伸ばし、呼吸をしてみると、骨盤底の筋肉が自然に反応して、わたしの頭と体幹は一つの調和へと導かれ、安定を取り戻しました。
驚きました。ヨガをしようと思っていたのではありません。
ロルフィングのムーブメントを考えていたハズなのに、結果的に同じ形に行き着いてしまったのです。
つまりあのヘンテコな顔は、先人たちが身体の仕組みを解き明かし、非常に合理的にデザインした結果だったということでしょう。
だから、身体の仕組みに沿って動いていけば、誰でもいつかは同じ形にたどり着く可能性があるのです。
実のところ、このような体験はこれが始めてではなく、以前から何度も体験していました。
わたしはそのたびに、ロルフィングとヨガの共通性に驚くとともに、人間の身体を設計した大いなる存在が示した一つの道、その叡智の一端にふれることに深い喜びを感じてきました。
股関節が固かろうが、やわらかろうが、そんなことは人が生きる上では瑣末なことです。
でも、自分を創造した偉大なナニモノカを身近に感じる体験。
それは、わたしたちの人生を変える可能性があります。
ヨガのポーズで必要とされる身体の動き。
その動きを生み出す身体の仕組みを学ぶことで、先人の辿った探求の道を、感動とともに、あらためて自分の道にしていくこと。
わたしがロルフィングのセッションや、講座を通してみなさんと分かち合いたいと願っているのは、まさにその一点です。
よくロルフィングは代替療法の一つとして紹介されるので、身体の不調を治す整体みたいなものだと思っている方もいるかもしれません。
しかし、ロルフィングの本来の目的は身体の困った症状を治すことではありません。
ロルフィングの開発者アイダ・P・ロルフ博士は、インタビューに答えて、こんなことを言っています。
「肉体的であれ、精神的であれ、症状の改善は第一の関心事ではありません。
それらを包含した上で、人間の潜在的な可能性を探求することにこそ興味があるのです」
わたしは、博士が残したこの言葉こそ、ロルフィングとヨガの親和性を端的に示していると思っています。