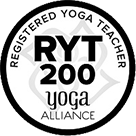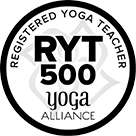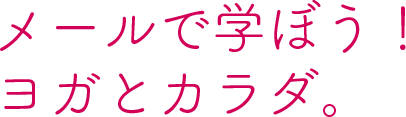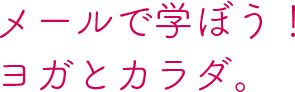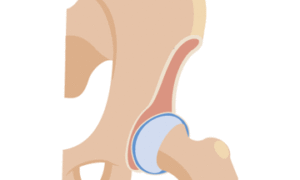ブログ,ヨガと体のQ&A,ヨガ解剖学 2016.10.17
ハラーサナでつま先が床に届かないのはなぜですか?
ヨーガのクラスでよく登場するアーサナのひとつにハラーサナ、鋤のポーズと呼ばれるものがあります。仰向けで行う逆転ポーズのひとつで、この形は小さい頃体操などで行ったことのあるような形でもあることから、馴染みのある動きのようでいざやってみると難しいものです。特に足先を床に着くのが難しいという方も多いのではないでしょうか?どうしたらハラーサナで足先が床に着くのでしょうか?体の仕組みから大きく2つに分けて考えてみようと思います。

ハラーサナ
ハラーサナで足先が床につかない要因のひとつに下半身の動きがあります。まずハラーサナの形を天地逆さまにして考えてみましょう。
逆転になっているときはわかりにくいかもしれませんが、これはいわゆる前屈の形と似ていませんか?

長座にして座った時に足を真っ直ぐに伸ばすことが難しく感じる方は、ハラーサナでも足先が床に着きにくいかもしれません。長座で座るためには股関節の動きが必要になり、そのためにはお尻や足の裏側にある筋肉の柔軟性が求められます。その柔軟性がまだ十分でなければ股関節は深く曲がらず、ハラーサナでも足が床から浮いてしまうでしょう。
そしてもうひとつは上半身の動き。
ハラーサナのときは肩が土台となり体を支える必要があります。腕を大きく後ろに回し、背中の上の部分、肩甲骨から土台を作っていきます。この時腕が十分に後ろに回せない方や肩甲骨を動かすのが苦手な方は土台が不安定になりやすく、肩で体を支えにくくなります。そうなると背中も丸まってしまいがちです。肩から腕でしっかりと床を押し、体幹の力でも体を支えることで足は動きやすく、また頭の方へと伸ばしやすくなりますので、この上半身で作る土台がなければ足先が床へ着きにくくなるでしょう。肩が十分に動いていないのに力で足を床へと近づけようとしても、背骨を無理に丸めて腰への負担になったり、首へ体重が乗ってしまい首への負担にもなりかねません。
それでは柔軟性や筋力が身につくまで行ってはいけないというわけではなく、道具を使って練習する方法もあります。

例えば、ボルスターやブロックなどを足と床の間に置いてみると、足先を床に着いている時と同じような感覚が味わえるでしょう。マットの上にブランケットを重ね置いて、その上に上半身を乗せて行う方法もあります。肩の土台を助け安定させることができれば背骨や首の負担も防げますし、足も動きやすくなりますので床に着きやすくなる方も多いと思います。
逆転のアーサナには上半身で体の重さを支える必要のあるものが多くありますから肩や腕に負担とならない方法を探すことも長くヨガを続けていくためには大事なことです。そのために道具を使う、というのも良いのはないかと個人的には思っています。
ハラーサナは肩周りや背骨、腰を伸ばしてくれるだけでなく、リラックスや疲労回復の効果などがあるといわれています。天地逆さま、逆転になるというのは心身へ多大な影響をもたらしてくれる動きのひとつ。まだ体が硬いから、といって行わないのはもったいないポーズです。体へと負担のかからない方法はヨガクラスへ参加してインストラクターに直接教えてもらうことをおすすめします。ぜひトライしてみてくださいね。
それでは、安全で快適なヨガを!
YogaBody